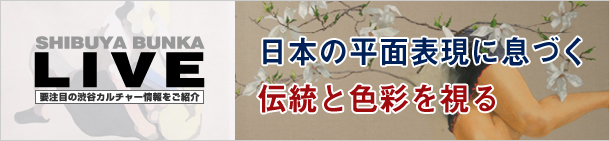Currently, in the Shibuya neighborhood is"Victoria and Albert Museum of Fine premiered Ukiyo-e Masterpieces Exhibition"-"Genre painting and nikuhitsuga"If, exhibition dealing with the Ukiyo-e has been held at the same time. Also,『特集 1960〜1970年代 日本のアヴァンギャルド アングラ時代のポスター展』に展示された60〜70年代を席巻した前衛的ポスターのデザインからも、どこか浮世絵的な色づかいや影響を認めることができるだろうし、"Tokyo-Ga ─ modest MY Fukei everyday"Also in the exhibition by a new generation of artists who have been featured in, a plane a few drawings and paintings of the lump to draw background was impressive.
Is the work of the Heian period beginning in the "wildlife person caricature", traditional painting representation of Japan seen in the Ukiyo-e in the Edo era, what is highly regarded at home and abroad as the roots of the current comics and animation is well-known as. Through these exhibitions, represented by the word Takashi Murakami was proposed "super flat", will be able to glimpse the DNA that flows through the draw included less unique to Japan painting representation of a flat plate. Also,"Allegory of put stuff ─AN ALLEGORICAL VESSEL"YaGallery es2 Exhibition of the work of being held in also, might be subject to or different impression when viewed attention to flatness and color sense. On this occasion, let us again review the flatness and color sense that alive in the tradition of Japanese art that is common to modern manga and anime.
 「冨嶽三十六景 凱風快晴」(6月展示)©V&A Images/Victoria and Albert Museum. |
|
| Ukiyo-e Exhibition of the United Kingdom of the Victoria and Albert Museum of Fine with one of the world's most ukiyo-e collection of 25,000 points. Hokusai Katsushika, Hiroshige Utagawa, from the popular ukiyo-e, such as Utamaro Kitagawa, until the color woodblock print by unconventional ukiyo-e, such as Kuniyoshi Utagawa and Kawanabe Kyōsai, precious masterpieces are on display. "Beautiful images and handwriting picture album of the young of Hokusai Katsushika, has been highly regarded as a very valuable material. It is attractions well as rarely without the existing block copy picture and fan picture." (Ota Memorial Museum of Art / charge person) | |
 Photo: mosquito nets beautiful woman smoking view (previous year exhibition) |
|
| Tobacco & Salt Museum from the handwriting painting drawn on until the 19th century collection is divided into the session before the late, we have exhibited about 60 points. Generally a structure in which followed the era, many of the works depicting the salt (salt production customs, such as salt pumping or grilled) are summarized in the late. In addition, the uptake in digital all stages (Figure), such as a picture scroll by using a computer, such as making the atmosphere to appreciate by hoisting the real thing, are elaborate. | |
 Venue Exhibition |
|
| 1960〜70年代にかけて主に演劇公演のために作られたポスターは、単なる「告知」の枠を超え当時のカウンター・カルチャーの先導的役割を果たし一つの芸術として位置づけられている。「これらのポスターには、アングラならではの遊び心が詰まっていて、エネルギッシュな時代を反映した自由度の高い表現が特徴的です。ポスターに負けず劣らず公演自体がどれだけアヴァンギャルドだったのかと想像させられます。」(Bunkamuraギャラリー/担当者) | |

左:細江英公+横尾忠則「薔薇刑(三島由紀夫)」2007年 シルクスクリーン 両者のサイン有り
Right: Akira Uno "The Little Prince" theater laboratory ceiling gallery 1968 silk screen
 Yukiko Suto "greening Mansion" 2004 |
|
| Exhibition to project now of "Tokyo" by young artists who worked in Tokyo Wonder site-related artist support program. Even during the exhibition takes the form that continues to make the place (site) by, for example, each writer is bring together the drawing, through the season sensibility Tokyo landscape, imagery, image derived is spun to the venue. It typified Gold to acquired Nara Enami with "GEISAI # 10", as if the depicted person or crowd in the mass of the margin many irregular, also looks like a map that represents of Tokyo, Shibuya of the "You are here" come. | |

Woodblock to 640 × 810mm paper Nara Enami "fight" 2007
 |
|
| Exhibition by New dimensional works of Chie Matsui. A new series of picture narrative works that dealt with jacket artwork was issued birth in the wake of the album "RISKA" of HACO, including the exhibition watercolor to center the oil at several points. | |
 |
|
| Human beings are inspired by the flora and fauna with the use of color and form that does not tired, even I think, the second solo exhibition of only Kentaro Kaneko, which has drawn so as to go knit without clearance by the pen a strong life force that has creatures. Loveliness, virulence, mysterious is, depicts breathing, etc., the overflow animals to life force. | |
 |
|
| "Yuku and things out before it noticed in you are living day-to-day change. Nothing would have passed a time to insidiously Being in without thinking. Nature is the growth to a change with the seasons. Find the change when was, I wonder if I myself was also undergone a change and growth, while such a ask myself, has continued to draw the plants and landscape. "(writer comments) | |