
■見出し・明治・大正時代はモダンな洋館が建ち並んでいた
・邸宅街としての静けさを保つ一方、再開発も進行中
・時代の変遷を反映し続けてきた洋館・内田邸
・48年前に来日した修道士兼アーティスト
※クリックするとエリア情報が表示されます
南平台エリアは高級住宅地ということもあり、どこか大人しい雰囲気がある。が、意外にも、日本の雑誌文化をけん引した制作会社がオフィスを構えていたり、若者の文化的コミューンがあったり、カルチャーの発信地となってきた歴史がある。さらに現在では、修道士として教会で活動しつつ、世界的なアーティストとして活躍する珍しい人物も——。
![]()

内田定槌邸 © 陣内秀信(法政大学工学部建築学科教授)
明治・大正期、南平台エリアに建てられた洋館の大半は、残念ながら戦災で姿を消したが、中には生き残って貴重な証言者になっている建物もある。その一つが、現在、横浜の山手イタリア山庭園に保存されている内田定槌邸だ。実に約1世紀にわたり、南平台エリアの変遷を見つめ続けてきた内田邸の建設年は1910(明治43)年。建築家のジェームズ・マクドナルド・ガーディナーにより、内田夫妻の意向をもとに、当時、アメリカで流行していたアメリカン・ヴィクトリアン様式を取り入れて設計された。太平洋戦争中の1942(昭和17)年、内田は77歳で世を去り、戦後、邸宅はQHQに接収されて米軍将校の宿舎として利用される。やがて米軍が去り、1957年(昭和32年)、内田邸に移転してきたのが「アド・センター」だった。その2年前、堀内誠一らにより設立されたアド・センターは、『平凡パンチ』『an・an(アンアン)』などの制作を通し、日本の雑誌にビジュアルの美しさや楽しさを初めて持ち込んだ革新的な制作会社。かくして内田邸は、当時の日本の若者文化の発信地となったのである。1972年、アドセンターは閉鎖するが、その後、カメラマンの立木義浩、ファッションブランド「ピンクハウス」の金子功、ファッションデザイナーの花井幸子など、ここから巣立ったクリエーターたちの活躍は目覚ましく、雑誌、ファッション業界に与えた影響は計り知れない。
ドロップアウトした若者の文化的コミューンの拠点に
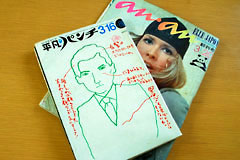
「アンアン」創刊号(1970年3月20日発行)と、同時期の「WEEKLY平凡パンチ」316号
さらに1968(昭和43)年、内田邸の敷地内の離れに「アップルハウス」が誕生する。アップルハウスとは、日本におけるビートルズのファンクラブであった「ザ・ビートルズ・シネ・クラブ(現在のザ・ビートルズ・クラブ)」事務局を中心とする反体制的なコミューン。高校や大学を“ドロップアウト”した若者が集まり、反戦コンサートやロック新聞発行など、枠にとらわれない反体制活動を展開していた。エディターの森永博志さんは、19歳のときにアップルハウスのメンバーになった。「当時は、高校を中退後、バイトしてお金を貯めてはヒッチハイクで放浪する日々でした。アップルハウスを紹介する雑誌を見て面白そうだと思って来てみたら、その日から寝泊りをしてもいいよ、って(笑)。音楽や映画や演劇や学生運動、ファッションなど、さまざまな分野のラディカルな若者が集まっていましたね」。やがて、森永さんは隣接するアド・センターで働くようになり、エディターの道を歩み始める。アップルハウスは1971(昭和46)年、その翌年にはアド・センターも閉鎖された。「アップルハウスは、高級住宅地の南平台のど真ん中にあったのが、何ともおかしかった。今思えば、幻想的なコミューンという感じでしょうかね」。その後、内田邸は、劇団の東京キッドブラザース、さらにデザイン会社のウォーター・デザインスコープなどの事務所としても使用され、1997年(平成9)年に現在の場所に移築される。翌年、かつてアップルハウスのあった離れは解体された。現在、その跡地にはマンションが建っている。
![]()

教会の密集する南平台エリアの中で最も歴史のある教会が、旧山手通り沿いのマレーシア大使館に隣接する聖ドミニコ・カトリック渋谷教会。伊達宗彰公の屋敷跡に建てられたこの教会で初ミサが行われたのは1959(昭和34)年12月だから、今年でちょうど半世紀の歴史を刻んだことになる。過去を紐解けば、巨人軍の長島茂雄氏が結婚式を挙げて話題になったことも——。実はこの教会、外観からは分かりづらいが、他の教会とは一線を画する特徴がある。なんと、100平米もの広さのアトリエが併設されており、修道士の一人がアーティストとして活動しているのである。その人物とは、今年79歳を迎えるガストン・プティさん。カナダのケベック州に生まれ、聖ドミニコ修道会で哲学と神学を学んだ後にカトリック司祭になったプティさん、1961(昭和36)年に31歳で来日したのが、日本との長い付き合いの始まり。「初めは日本語がまったく分からないし、見るもの全てが驚きでした……」と振り返るプティさんの日本滞在は今年で48年目。約半世紀にわたって南平台町の変遷を見つめ続けてきたのである。
マルチアーティストとして活躍

日本語で母親のことを「お袋」と呼ぶことに驚嘆したというプティさんの「O-Foukouro」シリーズの1作
母親の影響で子どもの頃から絵を描くのが大好きだったというプティさんは、1965(昭和40)年、教会内にアトリエを設けて制作活動を開始。ほとんど独学にもかかわらず、絵画や版画、壁画、彫刻、ステンドグラス、さらには教会デザインに至るまで次々に技法を獲得し、まさにマルチアーティストとして活躍するようになった。現在では、国内60ヶ所以上の教会や礼拝堂に作品が収められているそうだ。作品への評価は高く、松濤美術館や横浜美術館をはじめとした国内各地、さらにカナダやアジア、ヨーロッパなど、これまでに国内外で90回以上の個展を開いている。「教会に収める作品でなければ、必ずしも宗教をテーマにしているわけではありません」と、創作のスタンスを語るプティさん。コンピュータグラフィックを自在に制作するなど、いまだ衰えを知らぬ向上心と創作意欲が活動の原点にあるようだ。現在は姉の住むケベックにもアトリエを持ち、夏場はカナダで創作活動に励むことが多いそう。プティさんが創作した美しいステンドグラスや聖ひつは、カトリック渋谷教会に足を運べば誰でも自由に鑑賞できる。

森永博志さん
1950年生まれ。都立昭和高校卒業後、新聞配達やボート場管理などの仕事を転々とし、19歳でアップルハウスのメンバーに。隣接するアド・センターに出入りしていたのを機にエディターとなる。1976年、音楽雑誌『フォーライフマガジン』編集長となり、1978年、NHK・FM『サウンド・ストリート』初代パーソナリティになるなど、幅広く活躍。『やるだけやっちまえ』(リトルモア)、『ドロップアウトのえらいひと』『北京』(東京書籍)、『初めての中国人』(マーブルトロン)など著書多数。相棒を得たことで充実した人生を送る男たちの物語を集めた『one plus one』(仮題)を、今夏に刊行予定。

1949年、ドミニコ会・カナダ管区の宣教師4名が来日し、池尻教会を開設。1959年、伊達宗彰公の屋敷跡に建てられた現在の教会に移る。日曜日のミサは、8時、10時、18時の3回。
住所:渋谷区南平台町18-13

内田定槌邸 南平台にて。横浜への移築直前の佇まい © 陣内秀信(法政大学工学部建築学科教授)
個性派「南平台アジアマンション」の魅力って?  南平台アジアマンション外観 大使館や教会など荘厳な建物の多い南平台エリア。重厚な門並びに気圧されながらの取材中、どこかレトロな雰囲気が興味を駆り立てる建物を発見した。その名は「南平台アジアマンション」。ちょうど“南平台のへそ”とも言える、旧フィリピン大使館の向かいの7階建ての分譲住宅で、東京オリンピックを翌年に控えた1963年、第一次マンションブームの中で建設された高級集合住宅のはしりである。南平台に現存するマンションでは最も古く、今年で築46年。新築当時は庶民には手の届かない高嶺の花だった高級マンションも、時代と共に変化を遂げ、ここ最近では渋谷を中心に活動するクリエイティブ系企業の事務所としての利用が増えているとか。敷居の高い雰囲気が漂う南平台エリアにあって、どこかカジュアルで、若々しいエネルギーを放つ「南平台アジアマンション」——その魅力を探るべく、ここに事務所を構える人びとに話を聞いた。
南平台アジアマンション外観 大使館や教会など荘厳な建物の多い南平台エリア。重厚な門並びに気圧されながらの取材中、どこかレトロな雰囲気が興味を駆り立てる建物を発見した。その名は「南平台アジアマンション」。ちょうど“南平台のへそ”とも言える、旧フィリピン大使館の向かいの7階建ての分譲住宅で、東京オリンピックを翌年に控えた1963年、第一次マンションブームの中で建設された高級集合住宅のはしりである。南平台に現存するマンションでは最も古く、今年で築46年。新築当時は庶民には手の届かない高嶺の花だった高級マンションも、時代と共に変化を遂げ、ここ最近では渋谷を中心に活動するクリエイティブ系企業の事務所としての利用が増えているとか。敷居の高い雰囲気が漂う南平台エリアにあって、どこかカジュアルで、若々しいエネルギーを放つ「南平台アジアマンション」——その魅力を探るべく、ここに事務所を構える人びとに話を聞いた。
南平台から四季折々の食や植物の変化を発信  7Fのベランダからは、代官山〜恵比寿が一望 エディターの畑山信也さんは、10年前にこのマンションに移り住み、現在では最上階2部屋にて住宅と事務所を構える。同居人でフードコーディネーターのこてらみやさんと共に、料理本やガイドブックなどの雑誌、書籍の企画・編集を手掛ける『東京図鑑』を経営。マンション購入のきっかけは、偶然、この物件を売り出す立看板を発見したことだった。「『アジアマンション』という名前に魅力を感じ、『ジャケ買い』する気持ちで見学に足を運びました」と当時を振り返る畑山さん。角部屋の南平台を一望できる広いベランダを生かし、仕事の傍ら一年を通してガーデニングを楽しむ生活を送っている。ブログ「東京ベランダ通信」では、日々の野菜や草花の成長記録や、ベランダで感じる季節の移り変わりについて綴られ、南平台での豊かに流れる日常が垣間見える。
7Fのベランダからは、代官山〜恵比寿が一望 エディターの畑山信也さんは、10年前にこのマンションに移り住み、現在では最上階2部屋にて住宅と事務所を構える。同居人でフードコーディネーターのこてらみやさんと共に、料理本やガイドブックなどの雑誌、書籍の企画・編集を手掛ける『東京図鑑』を経営。マンション購入のきっかけは、偶然、この物件を売り出す立看板を発見したことだった。「『アジアマンション』という名前に魅力を感じ、『ジャケ買い』する気持ちで見学に足を運びました」と当時を振り返る畑山さん。角部屋の南平台を一望できる広いベランダを生かし、仕事の傍ら一年を通してガーデニングを楽しむ生活を送っている。ブログ「東京ベランダ通信」では、日々の野菜や草花の成長記録や、ベランダで感じる季節の移り変わりについて綴られ、南平台での豊かに流れる日常が垣間見える。
»東京図鑑
»畑山さんのブログ 東京ベランダ通信
»こてらさんのブログ オサルノビタミン
よりすぐりの1作品を、大きく広げる仲間たち  また、今年2月から新しくここの一員となったのが、『いのちの食べ方』などの配給レーベル「エスパース・サロウ」で知られる配給会社「新日本映画社」。隣の桜丘町に30年以上拠を構えてきた同社が、アジアマンションに引っ越してきたのはナゼか?「広さと家賃の折り合いがついたことに加え、玄関口の『アジアマンション』というロゴが面白かった」と語るのは、同社代表の甲斐秀幸さん。レーベル名「エスパース・サロウ」とは、フランス語で仲間を意味する「エスパース」と、砂時計を意味する「砂漏(さろう)」の組み合わせで、「世界中に無数にある作品から、砂時計のように選りすぐりの一粒を選んで、大きく広げて行く仲間たち」を意味する。実際に海外の映画祭から持ち帰った作品は「(エスパース・サロウの名の通り)みんなで話し合って評価し、配給を決めていきます」(甲斐さん)。この春公開予定の映画『キング・コーン』(イメージ・フォーラム)は、加工食品に含まれる「コーン」の実体を伝えるドキュメンタリー。『いのちの食べ方』『女工哀歌(エレジー)』から続く、消費の実体を暴く作風に対して、甲斐さんは「特にドキュメンタリーにはこだわっていない」と言い切る。そして「ただ、僕らが知らないことを単純に知りたいだけ。同じ気持ちを持っているお客さんが、案外多いんですね」と続ける。
また、今年2月から新しくここの一員となったのが、『いのちの食べ方』などの配給レーベル「エスパース・サロウ」で知られる配給会社「新日本映画社」。隣の桜丘町に30年以上拠を構えてきた同社が、アジアマンションに引っ越してきたのはナゼか?「広さと家賃の折り合いがついたことに加え、玄関口の『アジアマンション』というロゴが面白かった」と語るのは、同社代表の甲斐秀幸さん。レーベル名「エスパース・サロウ」とは、フランス語で仲間を意味する「エスパース」と、砂時計を意味する「砂漏(さろう)」の組み合わせで、「世界中に無数にある作品から、砂時計のように選りすぐりの一粒を選んで、大きく広げて行く仲間たち」を意味する。実際に海外の映画祭から持ち帰った作品は「(エスパース・サロウの名の通り)みんなで話し合って評価し、配給を決めていきます」(甲斐さん)。この春公開予定の映画『キング・コーン』(イメージ・フォーラム)は、加工食品に含まれる「コーン」の実体を伝えるドキュメンタリー。『いのちの食べ方』『女工哀歌(エレジー)』から続く、消費の実体を暴く作風に対して、甲斐さんは「特にドキュメンタリーにはこだわっていない」と言い切る。そして「ただ、僕らが知らないことを単純に知りたいだけ。同じ気持ちを持っているお客さんが、案外多いんですね」と続ける。
»新日本映画社
他にもこのマンションには、マイナージャンルの若い表現者に活動場所を提供するNPO団体「KOMPOSITOION」や、女のコカルチャー誌『girlie』の編集部「TIMEMACHINE Labo.」などが入居中。このように若くて面白い人々が集まるのは、古さゆえ比較的賃料が安いという理由もあるだろうが、結果的にこの場所が、かつての旧内田邸のような、新たなカルチャーの発信地として育っていけば面白い。
»KOMPOSITOION
»TIMEMACHINE Labo.