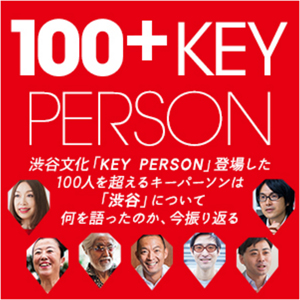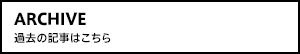Beside to be active as a musician, Shinji Tanimura that are also served as professor of standing in China, Shanghai Conservatory of Music. In the first times Shibuya music festival of November 19 also performs live, which collaborated with the next generation of artists as a "flag artist". The Tanimura's Shibuya of encounters and, the streets of change, also was interviewed, such as how the recent activity.
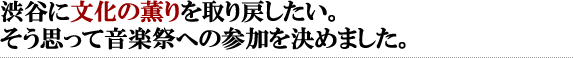
- Mr. Tanimura is, Do you have to Shibuya in any time.

Recently, or watch a movie, you often look for a book. The movie then you go to start a variety of cinema to "Cinema Rise", carries the often feet to "book first," the assortment of history-related books are substantial. In the old days you had a concert at the Shibuya Public Hall, but had come to Shibuya than now, it was pretty impressive changes and at that time. Especially around the cultural village street, or because began to different people of culture gather, are drifting international fragrance, such as New York and London. Just walking, I received a very stimulating. On the other hand from the center city was now receding feet. Previously, there is a conscious or implicit rule of "do not pollute the city", it had resulted in a "fragrance of culture" of some sort in Shibuya. It it is graffiti stands out by now, I will feel that stained the city by people who Hakichigae freedom. I think that it is a good place of Shibuya is because it is possible to "accept a variety of things", but if flip side, it is also the feeling that next to each other, such kana ... and the danger of moral. I like the alley, also abroad, I want to walk about the street that has been referred to as "this side is dangerous because not go" (laughs). But the street will change with the times, because there are still those "seems the town" in the back street. I will feel unfortunate in that sense has been lost quite atmosphere of the alley from Shibuya ....
- Did you change the impression of the people who walk the streets.
Even now I can not change the young people are often also a long time ago, so-called "adult" is I think you have fewer. It is, I wonder if has become a city that adults do not feel the coziness that. Of course, even a city that only adults gather will receive no impression of vibrant, but just because only young people will become as lawless. Fragrance of culture I think that rising from the city that young people and adults are present in a well-balanced. In that sense, it might have a little "bias" is now in Shibuya.
- In opened in Shibuya Public Hall on November 19, "the first time Shibuya Music Festival", it was decided to serve the "flag artist". It will took in what I think.

When you got the story, it was intuition Shibuya or not than regain the fragrance of culture by young people of our generation and the next generation is to interpose a music that plays together, and. When such as music and painting are interposed, because you can give them courage or heal or relieve human mind. Someone such a thing had been thought that what you need to do, I was raised their hands as a flag artist. Shibuya to recall the adult by the force of the music, I hope the new generation and communication Kizukeru. Now go to the live house Shibuya, most likely, it is the older I is the best in the customer. Lonely one person in the young people, such like there are in their 50s ... (laughs). It is also, I would be the cause of the young artists are many appearances. If so that is also referred to as adult artists, I think do a little change me that situation. I made a while ago, I sometimes played a secret live in the announcement of the day leaflets only in the "ON AIR EAST" at the time ( "SHIBUYA O-EAST" of the current). I'm the person who walks the city is not ... well known in the feeling like coming to the library, made the world's first DVD software that issued in 1990 by the Fuji TV and Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. software division and my It is tan. But there I at the time of the secret live video has been recorded, the "heat" of Shibuya of young people felt close to, I remember that was a good live.


- Mr. Tanimura is I think you have been a professor at the Shanghai Conservatory of Music from about three years ago.

Yes. I would've been us better understand the activities in Asia, which has continued for 25 years Chinese side. I met the Shanghai Conservatory of Music of Yang (Yang) director prior to accept the request of the professor. At that time, the director that was asked to me was the word "What do you Have a nice day I think the most important thing is for Mr. Tanimura music?". I, "" theory "is also" technology "is important also for the music. But, what do not forget than is I think it's" heart "," we reply with. At that time, I felt the "role" of a bridge between Japan and China.
- What are you what kind of leadership at the university.
We are talking about "music of a big meaning." It is "the heart to tell the music" is to become its center. For example, that students make up the stage joined forces. The instrument and amplifier to their own strokes setting, and firmly until the cleanup After completion. Simple, but it is obvious, I want you to feel very much and joy of "0 go creating something from (zero)" in it to experience the process. But it's easy to copy, to create the original is I want you to feel in a very difficult thing ... it is also the body.
- We are going do to continue any such activities in the future.
Youth started the music in mind that you want to be popular girl (laughs), and eventually married, pardoned the child, then has also means a lot of thinking to sing. And, also closed the office to interrupt the national tour made want to return all four years ago as one of the separators in white paper, I was there it is that you have the income to zero. But we need a courage, with the support of family when you empty your box, obediently, "Oh, my'm okay you doing," I was able to think on the positive. Maybe, it's was good that was to zero. When I leave I'm sure even in half, it would have had in such a state of mind. Or then say that the shoulder of the force is missing, if the will convey the music and the words to the people is their role, now it seems natural in the flow of time and come out "edge" It was. Now, I will obediently obey, and I think.
- This month, it was issued a new song "calendar of the Wind" for the first time in four years.
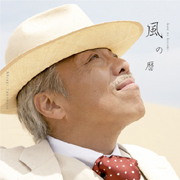
"Calendar of the Wind"
In that has been made so far about 550 songs, I wanted to much continue to make "Tabiuta". "Travel has the same meaning as life." I want to express as much "song" that. In such a flow that I wrote for the first time in a long time is a "calendar of the Wind". I was there by the time of their children, now gone, or eliminated while you want to keep properly what ... this time I'm "pinky" is one of the themes. "Recently, when was pinky?" And listen to me I "I wonder not much ...". I'm feeling is that I very deep commitment pinky. I mean, it is to drink needle thousand. Once you do that, but it will not be not very alive (laughs). But, "the person who pinky" ... that was all done normally is childhood but it is what "special person". Do not remember that kind of feeling, I think.
- Could you the last message in Shibuya in the future.
I, I think that I want you to aim the "town that adults and young people spend happily together." Only adults, young people only, instead of that, but it is important to balance. Someday It is why young people get older, I think that it is a very nice ... if in town that can connect a wide range of ages. Then rather than the idea of thinking the only thing Shibuya, or would not it important also to aim to coexist with the other town. Such activities are, I think opportunity of do that Shibuya is a nice town, I think I.
■ profile
Shinji Tanimura's
1948 Born in Osaka. 71 years, he formed the Alice. Collect the popular hit songs such as "winter of lightning," "now it is also another who," "Champion," but, stop the activity in 81 years. Then, we continue to express their view of the world through the classics, such as that it can be said that Japan's standard number "Subaru", "good day journey," "Sarai". And the London Symphony Orchestra, Opera National de Paris Symphony Orchestra, collaborated with the Vienna Symphony Orchestra, has been the life work exchanges with Asian artists. Served as a professor of standing at the Shanghai Conservatory of Music in China since 2004, it has committed to interact with youth development in Asia. September 13, 2006, released the "calendar of the Wind" for the first time in six years single.
Mobile site "Tanikomu Mobile" http://ccch.jp/tanicom
 |
1st Shibuya Music FestivalShibuya Public Hall and SHIBUYA MARKCITY East, Marui City 1F Plaza on November 19th. Shinji Tanimura "Flag Artist" and the bands recommended by 25 live houses around Shibuya Station are the charity events held at each venue. In addition, live at Shibuya public hall is charged (S seat = 3,000 yen, A seat = 2,500 yen, B seat = 2,000 yen). Saturday, September 23 (Sat) from 10 am on sale on electronic ticket Pia. |
Recommended articles

85年の東横ターミナルデパート物語

「渋谷サクラステージ」竣工へ 鉄道や幹線…

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

Shibuya with the spread of new coronavirus ...

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

東急百貨店本店がある間にもう一度見ておき…

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...