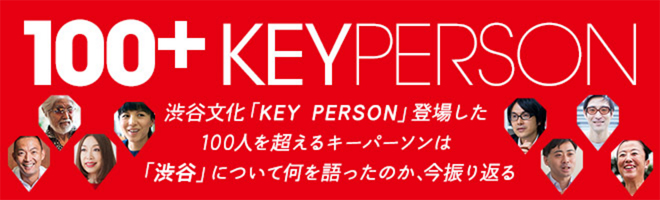Shibuya culture project
MENUKEYPERSON
渋谷は精神的に若いエネルギーのある人たちの街
そこから新しい価値が生まれるシンボリックな街になってほしい
株式会社エニグモ 代表取締役共同最高経営責任者須田将啓さん
プロフィール慶應義塾大学院 理工学研究科 計算機科学専攻 修士課程修了。2000年博報堂入社。マーケティングプランナーとして、大手企業からベンチャー企業まで幅広い領域のマーケティング戦略、ブランド戦略、コミュニケーション戦略の立案を行う。2004年2月、博報堂の同僚、田中禎人さん(代表取締役 共同最高経営責任者)とともにエニグモを設立。
「みんなで使えるモノは、みんなでシェア」するソーシャル・シェアリング・サービス「シェアモ」の運営などを手掛けるエニグモ。渋谷を拠点に、誰かのマネででなく、「世界初に挑戦」することを経営理念に掲げる同社共同最高経営責任者のおひとり、須田さんにお話しをうかがいました。
シェアモを立ち上げて1年。若い人のエコ意識への高まりを感じる
--シェアモが始まってちょうど1年ですが、この1年間はいかがでしたか?

シェアモにとっては、非常に順調な1年だったと思います。メディアでも想像以上に取り上げられましたし、幅広いユーザーにも恵まれました。「シェアする」という発想は、もともと時代の流れに合っているものだと感じていましたが、昨年はその流れが顕著な一年でした。洞爺湖サミットの開催に合わせて環境意識が高まりました。シェアモの考え方は、10年、5年前だったら「せこくない?」「けちくさくない?」といったネガティブな印象が強いサービスだったと思います。でも今は、シェアすることが家計だけでなく環境にも優しいという風に捉えられています。節約志向の高まりから、「無駄な物は買わない」「みんなで合理的に使う」ということが、ある種「かっこいい」「次世代っぽい」こととして、肯定的に受け入れられています。特に、若い人のエコへの意識が高くなっているのは、この一年の発見でした。
--育児関連用品などでの利用は多いと思いますが、それ以外ではどのような利用がありますか?
いろんなダイエット商品を試している方はいらっしゃいますね。ダイエット用品は、自分に合わないと使わなくなりますし、一方で、いろいろと新しいものも試したい。だから、まずシェアモで試してみて、気に入ったら引き取ってもいいし、合わなかったらまた次の人に回してあげるというかたちで利用されています。あとは、バーベキューセットとかパーティー用のドレスとか、宴会で使う着ぐるみとか、出し物用ビンゴゲームとか、その日限りで使い終わる物もよく利用されます。そういうものは従来、格安量販店で買って、使い終わったら捨てたり、タンスの肥やしにしてうることが結構多いですよね。そういう物はみんなでシェアしたほうが合理的ですし、家計にも環境にも優しいですから。
--田中さん(共同最高経営責任者)と会社を立ち上げたきっかけを教えて下さい。
田中とは、起業する以前にいた社内で同じチームでした。僕が居て、田中は僕の背中合わせのデスクに座っていました。僕は車担当で、彼は携帯電話担当。仕事での接点は全くありませんでしたが、年齢が一緒だったのでよく飲みに行っていました。そうした流れで、たまたま田中から面白いアイデアがあると言って聞いたのが、エニグモの最初のサービス「バイマ」の原型でした。同じタイミングで僕もちょうど別のアイデア持っていたのですが、「どこに居ても、そこに居ることが価値になって収入が得られる」という考え方を「バイマ」に感じて、自分の目指している方向性にすごく近いと思いました。いろいろ懸念点もありましたが、それは置いておいて「面白いから絶対やってみよう」という気持ちでした。それが2002年の年末で、年明けには二人とも企画書を作って持ち寄って話し合いを始めました。最初は「バイマ」について、サービスが出来上がれば自分たちが作らなくてもよいと思っていました。僕らに利益が出なくても、とにかくこのサービスを実現してくれる人がいればいいという気持ちでした。でも、結局、誰かに任せては思った通りのものは出来上がらないという結論に至り、お金を集めて我々で作ろうという判断をしました。会社を作ったのは29歳の時です。起業にあたっての覚悟とか決意とかはなく、ごく自然な流れでしたね。
--新しいビジネススタイルを確立していくにあたって、苦労はありませんでしたか?
起業も初めてだし、インターネットのサイトを本格的に作るのも初めてだし、全部初めてだったので、トラブルも失敗もありました。バイマは、そんな紆余曲折を経て、最初のアイデアから2年越しで、ようやく公開したサービスでした。しかし、初めは何の反応もありませんでした。そのとき、我々はすでに会社を辞めていましたし、しかも友人から集めた出資金はほとんど使っていました。その時はさすがに、「やっちゃったかも」みたいな空気が流れました(笑)。ただ、可能性は絶対あると確信していました。だから、時間はかかるが、とにかく大きく育てよう、と位置づけました。ただ、バイマ1本を育てているだけでは会社が成り立たないので、広告サービスを2つ作りました。それがすぐに売上が立ち、それで日銭を稼ぎながらバイマを育てました。そのバイマがようやく育ち、次のマーケット型のサービスをと考えて出てきたのが、シェアモだったんですね。
シェアモのアイデアは、街中に捨てられていたビニール傘から
--シェアモのアイデアが生まれたきっかけは何だったのでしょうか?
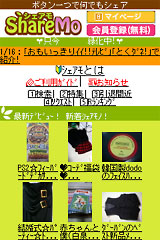
小さな話ですが、あるときコンビニで売っているビニール傘が、ほぼ新品の状態で街中に捨ててあるのを見つけました。その時、雨が降っていたので僕はその傘がすごく欲しかった。でも、それは間違いなく僕ではない誰かの傘なので、それを取って行ったら泥棒になってしまいます。僕は傘が欲しいし、傘を置いた人もきっと捨てるつもりで置いていった、傘にとってもゴミになるぐらいだったら誰かに使われたほうがいい。だから、その傘を誰かの所有物ではなく、みんなの共有物にしてしまえばいいと思いました。使いたい時に使いたい人が使って、終わったらまた次の使いたい人が使っていくという仕組みが合理的だと思いました。同じ観点で家の中を見渡してみると、使っていなくて邪魔だけど、捨てるのはもったいない物がたくさんありました。スペースも無駄だし、使える状態で捨てるのも無駄で、かといって絶対使わない。そういう物を、家に埋もれさせておくのではなく、みんなで開放して共有するマーケットがあれば、多くの人に有効活用されて、僕にとっても借りる人にとっても物にとってもハッピーだなと思いました。この考えを「シェアリング」というコンセプトに位置づけ、「シェアモ」を創りました。
--事業化するにはかなりのエネルギーが必要だったのでは?
シェアモは、すぐ利益が出るサービスではありません。僕は投資だと思っていました。そのため、最小限の人数でスピーディーに立ち上げようと、最初は僕とインターン生という2人コンビで、企画を練ってサービスをつくり上げました。新しい概念のサービスなので、固定概念に囚われたくないという意図もありました。企画が固まってから、サービスエンジニアリング本部やカスタマーリレーション本部などに意見をもらいましたが、そこに至るまでは、僕は社長業もありほとんど手を動かせませんので、ほぼそのインターンの女性1人でつくったことになります(今は社員となってシェアモを担当しています)。この体制のおかげで、既存の業務にほとんど影響を与えず、スピーディーにプロジェクトが進行しました。インターン生の新鮮な発想が吹き込まれて斬新なサービスになったと思っています。シェアモの企画でこだわったのは、とにかく金銭的なやり取りを一切無くすことでした。取引にお金が絡むと、どうしても「儲けよう」という欲望が出てきます。そうなるとオークションとあんまり変わらなくなってしまいます。ポイントも、ほかの物に換金できるような仕組みではなく、シェアリングにとっていいこと、シェアされればされるほどポイントがたまっていくような仕組みにしてあります。その辺の企画は、すごく議論して詰めていきました。
--将来的なビジネスプランとしての展望をお聞かせ下さい。

収益源は幾つもあります。一番分かりやすいのはバナー広告やリスティング広告です。試した人のレビューがどんどんたまっていくので、そこから買いたい人は買ってもいいし、シェアしてもいいという形です。我々としては、シェアで済ませる人も、シェアしてみて新品が欲しくなる人も、最初から新品が欲しい人もいると思うので、そこはどちらでもいいと考えています。あとはサンプリングという収入源もあります。サンプリングは、通常1,000個とか2,000個用意して、なるべく多くの人に配って広告効果を得るものですが、価格帯が高くて数が用意できない物だと、費用対効果が見合わない。しかし、シェアモの場合は、例えば100個サンプルを用意すれば、10回転で1,000人の人が使ってみることができます。20回転すれば2,000人ですから、今までサンプリングに向かなかったような商材や企業でも試すことができる。今までになかった収入源ではないかと思います。
--社員のアイデアを引き出すために、社風として意識していることはありますか?
当社は「今までになかった新しい市場を創ること、エニグモがあった世界となかった世界で明確に違う世界となっていて、それが今よりよい世界になっていること」を目指しています。このような会社の考えに共感できるかどうかを、入社への入り口にしています。入社後も、自分の意見を言いやすいように、どんなに入社年次が若くても、意見やアイデアに耳を傾けるようにしています。また、意見の言いがいがあるように、どんなレベルでもいいのですが、例えば、「こういう飲み会やりたい」「こういう制度を作りたい」という声が上がれば、それを実現させてあげるべく、なるべく努力しています。もちろんできないものもありますが…。でも、なるべく真摯に向き合い、新しいことを言いやすい環境と、それを言ったかいがあるようにと、意識して取り組んでいます。

Recommended articles

渋谷ヒカリエ開業10周年で「シブヤ・クロ…

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

85年の東横ターミナルデパート物語

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

The vitality of young people enhances the dissemination to the world. we…

夜しか食べられないフォトジェニックなパフ…

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...