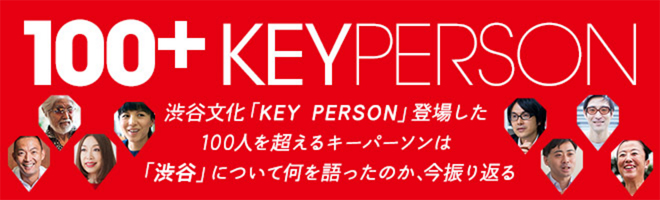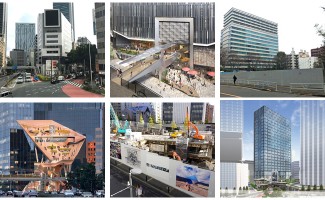Shibuya culture project
MENUKEYPERSON
Shibuya, all glue is mixture wriggle become 混然 town
That sloppy feeling, London also no match is also New York
Tomoyuki Tanaka (DJ · Producer)
profileTomoyuki Tanaka (Fantastic Plastic Machine)
Success at home and abroad as a DJ / producer. Own music style studded its own roots in dance music is supported by the world-wide, in addition to playing in about 50 cities abroad, serve as a DJ and music selection in various brands of the party, the show at home and abroad. In addition, FATBOY SLIM also as a remixer, James Brown, DJ OZMA, has worked the music, such as Kyoko Koizumi. Shinichi Osawa on April 29, 2009, ☆ with Taku Takahashi, released the album "trax" in producer unit · ravex (Ray Beck's) name to commemorate the avex20 anniversary.
Active at home and abroad as a DJ / producer, solo project "Fantastic Plastic Machine (Fantastic Plastic Machine)" Tomoyuki Tanaka to perform the musical activities in the name. Work pattern that DJ, longer relationship of Shibuya and the club is integrated, deep. We heard the appeal of Shibuya of the city in such Tanaka.
Mixture of feeling of Shibuya features all seaweed is wriggle become 混然 heck
- The first meeting of the Shibuya of the city?

Because I Kyoto born, I went for the first time in Shibuya I think it was at the time of 21 or 22. In 4-year college, I was doing at that time band, in order to appear on a live house that ink stick in Shibaura, went to Tokyo by car along with bandmates from Kyoto. Meishin, in Noritsui Tomei, entered the Tokyo Metropolitan .... When you are toward the city center from Shibuya, Tokyo to "WAVE", which was previously the location of the now of Roppongi Hills called "Neubauten" is a large banner of the Group of Germany it has been multiplied by the visible from the capital appreciation, "Tokyo, wow I remember that I thought it was Do not "place. At that time, in that around the various places in the band colleagues and the car, we went for the first time Shibuya. Because it was a music lover, or go to the record shop in Shibuya, or go to the curry shop ... really, it was just a "country cousin" (laughs).
- The first of Shibuya impression?
Because I Kansai of human beings, a multi of the people of Osaka Shinsaibashi level had always experienced. But, Shibuya guess I was not just no way, white on the number of human beings, what the white .... Record shop also really "Do not sell anything, here," was the image of. Every record around the world, for example, something like one of the phantom is said to be rare record, is a Shibuya record shop have sold in cold blood, a single vision, we have is with of course a good price , If you bought the customers that it is such ... such an image so that one should have been a phantom from the back of the stock is replenished. Than in Paris, France When was I buy French record, it was felt that in Shibuya ... than Los Once was I buy hip-hop in Los Angeles. Music as a material had been very substantial.
- Compared with at the time, Shibuya of image do you have changed?

In terms of musical point of view, it was reducing the record shop now. Still, a large CD shops, such as become a landmark Tower Records and HMV, if there is a little more scale of small shops to accompany it, because there is also a maniac used Ban'ya's Toka of specialty store. Course record shop is also in the Nishi and Ochanomizu, but Considering the number Toka tension level of the people, and the feeling that still wonder if Shibuya of the .... Shibuya is not limited to the genre of music, there is a crucible like a impression of extremely different culture even now. Not only one of the glue, wriggles all glue becomes a 混然 heck, mess, Do not have anything, I feel a mixture is, it is still Shibuya features. Upon exiting overseas made the music, we are still be called the word "Shibuya-kei", but in Japan, I often refer to a mixture ish music of the '90s Speaking of "Shibuya-kei", in South Korea, Toka so-called Japan's dance music Toka dance pop, kind of new edgy music has been enclosed in the word "Shibuya-kei". Words to even nostalgic feel no longer used anymore in Japan, because well-known as a word that indicates the state-of-the-art Japanese music in Seoul, it is a little strange feeling.
- Club scene in Japan Do you have any movement now?
It is very diversified. Anymore, because "this box is such a person has the stomach ..." rather than the era, the sound varies in the evening of DJ and organizer unit, very wide variety. I think that the layers became thicker. It is often thought to have fallen even tension of club culture gone analog record, but the people who play in the club to the contrary is feel like are increasing. For example, as people in large-scale music festivals, such as "Fuji Rock" is flowing, among the CD has previously about is no longer sold, I feel like everyone is looking for something like a "live feel". Elation and musical live feeling in the field, because there is no one available at delivery ....
- Have you ever dine at Shibuya?
How can often be a meal from ending event in the morning, I Shibuya of food, do not sleep really. Soba shop under guard, Hakata, ramen shop of Osaka are also doing in 24 hours. Ramen shop of Sapporo It also opened up quite early in the morning. 24 hours a day and, late at night, the store is doing until the early morning is me many town to there, I think I no other also looking for around the world. Just really are in Shibuya, those Gotochi of Japan is I think you can taste at any time. Good to go, Toka soba shop is open 24 hours a day called "noodles KAWAKEI" .... The is is put even anything to say soba noodle restaurant, but, was like being used may be those of the DJ, you or apparent that the record back are lined up a number in the shop.
Shibuya of club play in peace location. I want to do the young people also put club event
Do you have increased the number of people that the --DJ?

In the past, I think the young people that are pulling the rattle and record back was obvious Even DJ. Because I could not go to be up and down the stairs with the record back with a 20, 30 kilometers to go to the club, physical fitness is also required. It's a costly further analog record is heavy, it properly to you collect do the music, it took both time and effort to some extent of the money. But now the people that use the analog is reduced, it has been turned into a digital sound source in the CD and data. It is the same as the cameraman's is no longer used film. So feel free to increasing number of people to start a DJ, I feel like it is no longer the never a special profession. Because the girl I went two or three times in the club will also listen to say things like "What do I DJ." However, I'm thinking so as not to be as simple to there. We very think Professional Occupation even now.
- Do you think that should I expand on how the future, the club?
People who do not even know you many, but the club house to the dance by now of Fueiho is made to customs business treats, open until dawn has become to the rules do not. Operating as a restaurant is being allowed, but to dance in music in the middle of the night has become a sin. But, I get caught in the law just by dancing sounded the music, I think that funny. Club, because it is where the money is moving while the other recreational facilities are closed, I think that in terms of economic effect significance there. By activating the more club, I think I Do not I wish you will be rewarded by sales recognized in the country. That way, also makes it easier to go to play someone who did not go to the club until now. In that late-night is, but I think that of course there is also the economic effect of the karaoke shop like a place, to leave even drink at the club, and or buy a download or CD if there favorite music, the two also in the following manner we think that there is a possibility that the move is money.
- Please let the problems are having the club.
At present it is that the following of people 20 years of age go to the club has been regulated. Sure you might be a child is not good to go to a place that would buy you a drink easily, but to be able to go to the club even in young people, to dance and enjoy the music is free ... to the fact that I think that should I become. The most impressionable time Nante not meet to dance music and club music .... So, I I want to do a club event to put the young people. Of course, illegal activity does not go. Toka smoke cigarettes Toka drinking, Toka there is Nampa after excessive .... But, for example, while allowing the admission of more than 18 years of age, always try to minors can not buy a drink in the wristband system, and I think that measures there. Club is a really tend to think that it is unhealthy place, to not remain silent shops if there is such a thing, Shibuya of the club is a very safe and secure play place. So, I been law a little more development, and play in young people is also the club, and if the wind that it is to dance in the middle of the night and adults not to sin, we hope to off the dance music as a human being to work.

Recommended articles

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

若者の活気が、世界への発信を高める。僕ら…

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

"Hachiko and the faithful dog Hachiko statue" exhibition in progress!

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

85年の東横ターミナルデパート物語

Shibuya with the spread of new coronavirus ...