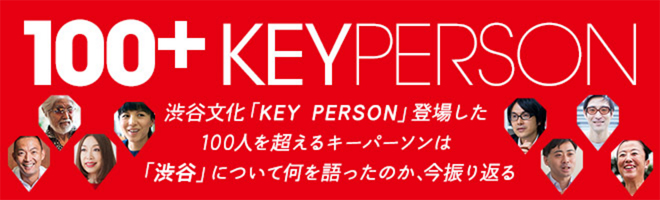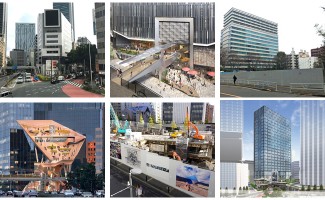Shibuya culture project
MENUKEYPERSON
The building is covered with "Information coat", the stage from the basement up to the burn,
Scramble intersection itself changed to "huge event space"!
Tokyo City University, ProfessorKazuo Hiramoto
profileKyoto University Graduate School of Engineering, Department of Architecture and Architectural Engineering Graduate Degree. Doctor of Engineering. Mitsubishi Research Institute, city management director, director of Human-Environment Research Division, served as the Tokyo University of Technology media undergraduate professor. So far in the Tokyo waterfront sub-center, Seoul urban redevelopment, planning of various projects such as urban planning of Malaysia information city, engaged in promoting commercialization. Since 2009, it became the Tokyo City University life city Faculty Dean. In addition, such as to concurrently also lecturer of the Tokyo National University of Fine Arts and Music, Graduate School of Fine Arts Department of Science and Waseda University Graduate School of Creative Engineering Department, focus on the development of backward as a specialist of urban planners. The main book is "Tokyo Project" (Nikkei BP), "Coastal Fukutoshin Story" (Chuko Shinsho), "advanced information and urban and regional development" (administrative), "now this happens Tokyo" (PHP), such as.
City life Faculty website
In April 2009, the newly established "urban life department" to the Tokyo City University (formerly Musashi Institute of Technology). It makes a clear distinction from the conventional Department of Architecture, management necessary in considering the "urban development", to cultivate a city planner with the science and the humanities and both of knowledge you put the base to the management, Japan's first "town planning department." I. Kazuo Hiramoto Professor dean of the same faculty, Odaiba ever (waterfront sub-center), Yokohama Minato Mirai 21, involved in the planning of the Aichi World Expo, Omotesando fashion hub development, making the beginning a number of the city of Seoul city redevelopment People have been. In this key person, welcomed specialist at is Hiramoto professor of this "urban development", in addition to the "Shibuya of the future of 2030," a summary in the same department in September 2009, for more information about what is needed now in Shibuya I heard a story. Shibuya after really 20 years, do we achieve an integrated How transfiguration?
Shibuya resources, lies not a neat thing, such as "five Sa Road" and "love hotel"
- Shibuya of future image was set to "2030" is Why?
About the future of Shibuya, until about 10 years into the future is a realistic plan, such as railway companies and government have almost decided. From the fact that thought trying to do in looking not involved at all with it, we are approximate overview of a further 10 years in 2020, which is visible to "2030" in the subject.
- Please tell us about the process of up to show the future of Shibuya.

First, in the near future, the Toyoko Line will connect with Shinjuku by entering the FUKU-TOSHIN LINE , so there should be competition with Shinjuku. There are also large commercial areas such as Roppongi and Ginza nearby. The first thing I thought was that "What is the uniqueness of Shibuya?" For example, if you compare Shinjuku and Shibuya with just numbers, it is clear that there is a business district and Shinjuku where the working population is large. Under these circumstances, when I examined the history and topography of the city so far, I could see that Shibuya was a "valley". Shibuya Station is the most concave in terms of topographical shape, and the road is radial and concentric. For that reason, it is difficult to build a large building, and it also features chaotic points. In the discussion within the department, there was also a moderate opinion, such as trying to bring a more branded shop, or building a convention center in the center of Shibuya, but while thinking about things that only Shibuya can do, "Shibuya The fact is that the fun of is not in an orderly way. " For example, there are a lot of love hotels in Shibuya, so if you discuss and think about both the proposal to regulate and eliminate love hotels and the idea to use love hotels, it turned out that it is an interesting resource that there is just that much That's the process.
2030, Shibuya is "1 second city" to variable
- After 20 years, the building of Shibuya or changes to the specifically how?

In the scramble crossing, installed a large vision of four, the advertisement video flows constantly
Rather than the image of the buildings architectural design house has created a total of something like the screen was Mashi account the future buildings, such as to be covered. How we can close the digital signage now of Q-FRONT, in a state in which the information covers the building like a film, I have named it "information film". If the link from a state in which the pieces of the building are arranged in the communication network to each other, it is also possible that Utsushidasu in a state in which the connected as one large screen. Do you remember there was a large screen of 360 degrees at the Beijing Olympic Stadium? Also in Shibuya of the city, I think it can be.
- I will very concept of traditional buildings instead.
I want to go with the feeling of "about to leave and bury the building!". Of course buildings but I of course there is, in all wall electronic media, or creating a wall of virtual temporary, quickly or lost it. Since the color of the wall is also light and dark is also a variable if you use the electronic display, the town up to now, it should come it finished the figure that was different from the architecture of until now. Although the life of commercial construction is said to be about three years, it is Shibuya in the future change the architecture and the city in units of 1 hour and 1 seconds figure "1 second city".
- "ShibuChika" What will become of the underground shopping center?
The underground shopping center, we thought it is better that there is an open space part to some extent the sky is visible. Or there is an atrium that is the sun not look of being covered with the concrete ceiling, or there is a part that seen through the ground. Then, those hydraulic large elevator like a of, big stage from underground is coming up and burn. Here performs a live concert and, further in conjunction with the large display, you scramble intersection itself is completely changed into a huge event space.
What happens if the ad group that integrated around Shibuya Station -?
It will increase the "three-dimensional advertising," such as video and signs that float in the air. For example, 3D space as well because you can make easily by or out of the water vapor, is the extent technically possible. The worldwide celebration of computer graphics in the United States has been held every year "SIGGRAPH (SIGGRAPH)", has already been introduced many such a 3D ads. Signal also changes to the three-dimensional LED signal indicator that is projected in the air space. Of course I will think whether can not afford to simple things the police jurisdiction, I will feel that's like a sign board not it will 3D conversion proceeds. Then, the earlier of the exhibition, such as "SIGGRAPH (SIGGRAPH)" It is good if the venue Shibuya of the city itself, not the facility. If Ikere tailored Shibuya to experimental place of digital media, the former as a bit Valley, I think in a unique person who is an opportunity to come together in Shibuya. However, rather than engineering ones such as Akihabara, a little better of media content closer to the art, I think that seems to Shibuya. Still I wonder if the industry associated with it, and we stuck to the periphery of Shibuya of the town, not the Shibuya bring their own power.

"Video City" and as a starting point a keyword or image, such as "facial expression changes Square every second", Shibuya Station neighborhood future image visualize
CG production: Corporation Premium Agency
"Shibuya of 2030 future will change this."
■ "Information coat"
The walls of all the buildings will be digital signage suffered the information media. By linking the building to each other, the whole city is changed to one of the giant screen. The color of the building, the design variable it is possible to instantly.
■ "three-dimensional advertising"
Subject of advertising is changing from the era was the printing of the paper to the three-dimensional image by the image projection technology to the fog-like gas or a multiple acrylic plate.
■ "three-dimensional LED signal-label"
And pedestrian signal, labeled etc. are also projected from the ground. Or occupy the physical location, on top there is no consumption, it is easy to update the information, innovative next-generation infrastructure that will disappear when not in use.
■ "faithful dog Hachiko (video)"
Future of Hachiko, the video that ran around the peripheral Shibuya. In artificial mist that is released toward the inside of the square from the buildings surrounding the square, the video of Hachiko is projected to run around lively.
■ "ShibuChika"
Image right underground in front of the intersection, a new "ShibuChika". Stage and rise to the ground by a hydraulic elevator, which media to capture the line of sight of building the wall surface of the information film buy to go people to project live in, change and rattle the image of today's branch underground.
Recommended articles

新たな再開発エリアの注目は「道玄坂」 新…

東急百貨店本店がある間にもう一度見ておき…

"I examine the microorganisms that live in Shibuya, the next generation city ...

85年の東横ターミナルデパート物語

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

Shibuya with the spread of new coronavirus ...