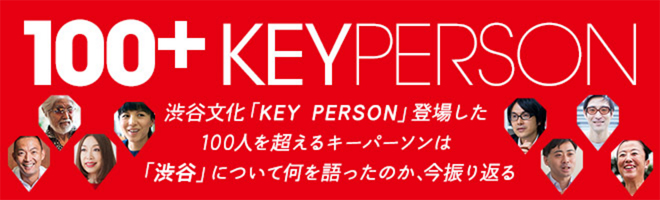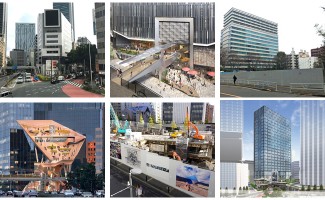Shibuya culture project
MENUKEYPERSON
渋谷の街が一つのカラーに染まる──「渋谷音楽祭」がそんなイベントの一つになっていけば…
アーティスト近森基さん
プロフィール1971年東京生まれ。1995年慶應義塾大学環境情報学部卒業。1998年筑波大学大学院修士課程終了。1999年ポーラ美術振興財団の助成を得てカールスルーエ造形大学(ドイツ)に留学。1996年より久納鏡子さんとの共同制作を開始し、「Ars Electronica」をはじめ、国内外で多くの展覧会に出展。メディア・プロダクツ・ユニット「minim++(ミニムプラプラ)」としても活躍。2004年、有限会社plaplaxを設立。メディアアート分野にとどまらず、遊び心あふれるプロダクトや絵本等も発表している。
11月11日から、渋谷C.Cレモンホールなど渋谷の街中で開催される「第2回 渋谷音楽祭」。そのアートディレクションとポスターデザインを担当するのがアーティストの近森基さん。メディアアートのさまざまな分野で意欲的な作品を発表する一方、遊び心あふれる絵本やプロダクトも発表する。近森さんが感じる渋谷の街とは。
渋谷はそのときそのときによって、頻繁にアクセスする場所が違う街
--渋谷の街との関わりや印象は?

生まれは東京ですが、育ったのは横浜です。自主的に渋谷に通い出したのは高校生の頃で、学校のある日吉から東横線で渋谷に遊びに来ていました。その頃はチーマー全盛期で、怖い感じがしていたのであまり一人では行かなかったですね(笑)。今はよく仕事の合間にHMVやタワーレコードなどで片っ端から試聴してまとめて買っていくことがありますが、小さい頃には父親に連れてこられて東急文化会館に来た思い出があります。そのときそのときによって、頻繁にアクセスする場所が違う街ですね。渋谷の中でもちょっと場所が違うと、アグレッシブな場所もあればそうでない場所もあるように、一言で渋谷の文化を規定するのは無理だと思います。
--「渋谷音楽祭」については最初どのような印象を持ちましたか?
広い領域でのプロジェクトとして、音楽祭から広がる文化の発信などの企画に関わりたいと思っていました。昨年行われた1回目の音楽祭よりお話をいただいており、実際に見に行ってみたら非常に面白い場だと感じました。演奏しているバンドはロックだったりするのに、客席では若者や年配のお客さんがある種の一体感を持って場が形成されている。渋谷は偏って見られがちですが、その場にひとつの可能性を感じ、もっと何かできるのではないかと思ってステージを見ていました。単純に音楽だけのお祭りをやるということではなく、「アートイベント」の方にも広げていくのも面白いのではないかと思いました。
フェスティバルは、10年20年と続くことでインターナショナルに認知されていく

--今回のポスターのテーマは?
海外のアートフェスティバルや音楽フェスなどに参加しても感じることですが、こうした企画は継続することが大事だと思います。最初は有志が集まって細々とスタートしていくが、10年20年と続くことでインターナショナルに認知されていく。そうして初めて、そこが発信していく文化になると思います。昨年のポスターを拝見して、何か受け継げるものがないかと探したときに、印象的だったのがピンク色でした。渋谷のアクティブな側面、活発な力を感じる色であり評判も良かったので、「渋谷音楽祭」のキーカラーとして残していくことにしました。
--「猿」をアイコンにしましたね…。
この先に続けるにあたって、アイコンになるようなものを作ろうと思いました。毎年ある時期になるとそのアイコンが渋谷の街に現れてくることによって、「今年も何か始まる」というわくわく感を高めていけるのではないか。そこで直感的に思いついたのは「猿」のイメージだったんです。スタッフジャンパーの背中などにピンクの猿が描かれていて、渋谷の街中を歩いていたら、ピンクの猿にジャックされた感じが出るのでは(笑)。山手線を思い描いたときに西南西の方角が申(=猿)にあたることもわかりました。ハチ公やモヤイ像のような既成のキャラクターではなく、新たな動物を考えたときに、猿の自由に動き回るようなアクティブさ、雑踏やジャングルの中を縫って歩いていく姿が思い浮かびました。もう一つは「吠え声」。テナガザルには群れごとに特殊なフレーズのようなものでコミュニケーションをとっていく習性があるそうです。誰かが歌い出したときに、その声に街のエネルギーが呼応していくイメージですね。音楽祭でもバンドという形態が多かったことも印象に残り、ある種のチームを作って奏でていくということも重なりました。猿を3匹にしたのは、音楽祭のコンセプト「3 little words」から。「見ザル言わザル聞かザル」じゃないですけどね(笑)。
--2回目の渋谷音楽祭に期待するものは?
渋谷ということで、音楽も一つのジャンルではないと思うんです。パリで毎年やっている音楽フェスティバルがあるんですが、街中至る所の街角で音楽をやっても、石造りなので通りを1本隔てるとほとんど音が混ざらない。渋谷にはいろんな音楽があっていいので、ブラスバンドやパーカッションなど、何でも受け入れられるような形になれば面白いと思います。ごちゃ混ぜというのはすごく東京的・日本的でもあると思うし、渋谷発信の文化をいかにして作っていくかを考えると、「音楽」をキーに、映像や絵画で音楽表現をできるかもしれない。この先、いろんなメディアを横断することをやってみても面白いかなと思います。

東五反田の「Galerie Teo」で開催された「motoyoshi chikamori ++ kyoko kunoh」展より
Recommended articles

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

"Hachiko and the faithful dog Hachiko statue" exhibition in progress!

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

85年の東横ターミナルデパート物語

新たな再開発エリアの注目は「道玄坂」 新…

Raising tension before commuting to work "Early morning festival ...