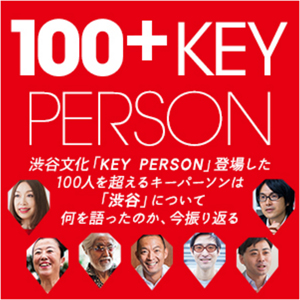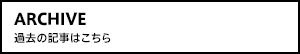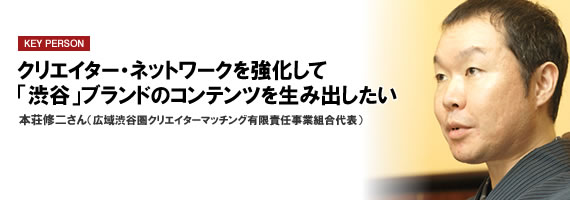 7月1日,活躍在“廣域澀谷區”的創建者和SNS網站“XSHIBUYA(交叉澀谷)”,以符合公司打開。本莊修二對自己在擔任其代表,也是在廣域澀谷的辦公室,你Irasshai涉及範圍很廣,如IT相關業務的諮詢服務。本莊女士和XSHIBUYA的目標,我們聽到了,我覺得到澀谷。
7月1日,活躍在“廣域澀谷區”的創建者和SNS網站“XSHIBUYA(交叉澀谷)”,以符合公司打開。本莊修二對自己在擔任其代表,也是在廣域澀谷的辦公室,你Irasshai涉及範圍很廣,如IT相關業務的諮詢服務。本莊女士和XSHIBUYA的目標,我們聽到了,我覺得到澀谷。 
※SNS(社交網絡服務)...每個其他與會者介紹朋友,已建立了擴大網絡的目的站點。在日本,如“mixi網(mixi網)”而聞名。而且,任何人都可以自由參與服務,存在如果沒有引薦不能參與一服務。 XSHIBUYA後者。
--XSHIBUYA是Meiutsu一個“廣域澀谷區”,做什麼樣的the'll的形象?

通過--XSHIBUYA,做我們預計澀谷是如何變化的。一個是我覺得在國外傳播澀谷有很大的影響。它實際上好讓前來澀谷,只是往往不知道只是走在街上。例如,唯一的日本代表團遊覽辦公室還參觀了矽谷,企業不理解的本質。在這方面,如果除了XSHIBUYA,很明顯是你是否有什麼活動澀谷創造者。進一步向內,向創作者分佈式出生通信體驗過,將它誕生的自由引領,重點澀谷區中的作用。如果出現這種情況,包括不同行業創作者的合作,我們預計將在各個方向的膨脹潛力。

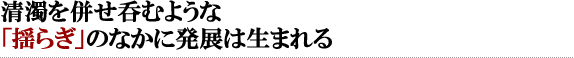 - 請介紹一下本莊山和澀谷的相遇。
- 請介紹一下本莊山和澀谷的相遇。

- 請介紹一下澀谷的IT業務的當前狀態。WEB2.0(※我的第二代管理層的時代已經增加的)。有不低於20代的那一代。在另一方面也一直積極與脆脆的第一代經理人從投標谷的時候。此外,它成為了驅動力發動XSHIBUYA是管理的第一代誰。他們,或通過創建這樣一個網站,進一步了解大家一起合作的重要性,回饋社會,似乎還有就是你想這樣做的具體形式的感覺。但總是年輕人澀谷一直活躍在精力充沛,即使在第一代的管理已經成為所謂的未來高級的年齡,我認為具有廣泛的年齡組的希望,一個地方都可以發揮積極的作用。
※WEB2.0...被統稱下一代網絡的方式詞。雖然明確沒有定義,通過堆疊的利基需求“長尾理論”獲得較大的銷售,促進基層交流,如“博客”,“SNS”經常被援引作為一個具體的例子。
- 未來,在澀谷,你以為我要你的目標是什麼方向。

■簡介
本莊修二
出生於福岡縣。工程畢業學部東京大學。另外在賓夕法尼亞大學沃頓商商學院的工商管理碩士學位。目前,泛大西洋開展IT企業的投資和發展:在服務於日本代表(總部美國康涅狄格州)的,由本所辦公室工作的諮詢與IT相關的新業務。此外七月並發還代表門戶網站“XSHIBUYA”在一天內打開。
XSHIBUYA
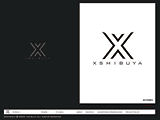 |
由於SNS服務和網絡雜誌,擴大與創作者和企業的配套業務。我們預計1萬多創造者和合作夥伴的第一年參與。由商務部東京商會委託和操作行業廣域澀谷區的創作者配套有限責任合夥(LLP)。 http://sns.xshibuya.jp(SNS) http://www.xshibuya.jp(WEB雜誌) |